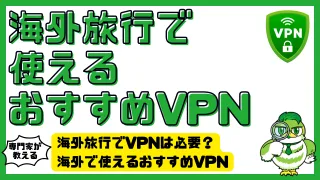本ページはプロモーションが含まれています。
目次
オーディブルのデメリット|結論から言うと「使い方次第」
オーディブルには確かにいくつかのデメリットがありますが、それらはサービスの特性を正しく理解し、自分に合った使い方ができるかどうかによって評価が大きく変わります。たとえば「聞きたい作品が見つからない」「頭に残らない」といった声もありますが、それは使い方を誤っていたり、自分のライフスタイルに合っていないだけかもしれません。
特に注意したいのが、オーディブルは「耳で聴く」読書体験であるという点です。紙の本や電子書籍と違い、視覚情報がなく、手を使ってページをパラパラとめくることもできません。そのため、読書に集中しづらい環境や目的に合っていない場合、「使いづらい」「損した」と感じることもあります。
たとえば、通勤中や家事の合間に耳だけ使える人にとっては、オーディブルは非常に効率的な読書ツールです。しかし、図解や表が多いビジネス書や学術書を深く理解しようとする場合は、逆に効率が悪くなることがあります。このように、オーディブルが「便利」か「不便」かは、何を聴くか、どう聴くかによって大きく変わってくるのです。
また、コンテンツの選び方も重要です。聴き放題の対象外作品が多いという声がありますが、これはKindle Unlimitedのような読み放題サービスと比較すると顕著です。とはいえ、オーディブルにも20万冊以上の聴き放題作品があり、話題の書籍や小説も数多く含まれています。自分の興味や読書目的に合わせた選び方ができれば、十分に満足できるラインナップです。
さらに、ナレーターとの相性や再生速度の調整など、細かい使い勝手の部分も見逃せません。一見不便に感じる部分も、アプリ設定のカスタマイズや機能の使いこなしで解消できることがあります。

結局のところ、オーディブルのデメリットはサービスそのものの欠陥というよりも、「ユーザー側の目的やスタイルとのミスマッチ」によって浮き彫りになることが多いです。向き不向きは確かにありますが、自分の使い方に合うかどうかを見極められれば、デメリットを最小限に抑えて快適に利用することができます。
【30日間の無料体験はこちら】
audible(オーディブル)公式サイトはこちら
デメリット1:聴き放題の対象作品が少ない
オーディブルは「聴き放題」とうたっているものの、すべての作品が対象というわけではありません。実際には、最新のベストセラーや話題のビジネス書など、多くの人気作品が対象外となっているケースがあります。
さらに、Kindle Unlimitedと比較すると、対象作品数の差は歴然です。Kindle Unlimitedが約500万冊を提供しているのに対し、オーディブルは約20万冊と、その差は実に25倍。読み放題の感覚で探しても、「聴きたい本が見つからない」と感じる人も少なくありません。
これは、オーディオブックの制作にコストと時間がかかるという性質上、数を一気に増やすことが難しいためです。文字の書籍であればデータ化して配信するだけですが、オーディオブックはナレーターの朗読や音声編集など、多くの工程が必要となります。
そのため、オーディブルでは「数より質」を重視する傾向にあり、有名作家による書き下ろし作品や、芥川賞・直木賞の受賞作といったクオリティの高いコンテンツがそろっていますが、利用者にとっては「選べる幅が狭い」と感じやすい点も否めません。
特定のジャンルや著者にこだわりがある場合は、対象外であることにがっかりすることもあるでしょう。事前に聴きたい作品が含まれているかを公式サイトで確認しておくことが大切です。
オーディブルを最大限に活用するためには、「月額1,500円で何冊も聴ける」というメリットだけでなく、自分が求める作品がラインナップにあるかどうかを見極めることが重要です。選べる本の数に期待しすぎると、契約後に「思ったより少ない」と感じてしまう可能性があります。
デメリット2:単品購入が高すぎる
オーディブルでは、聴き放題の対象外となっている一部の人気作品や新作については、単品での購入が必要になります。このときの価格が、紙の本やKindle版と比べて明らかに割高になることが多く、コスト面で大きなデメリットと感じる人が少なくありません。
たとえば同じ作品で比較してみると、紙の本が1,800円、Kindle版が1,700円であるのに対して、オーディブル版は会員価格でも2,400円前後というケースが珍しくありません。非会員だとさらに高く、3,000円以上になることもあります。30%の割引があるとはいえ、音声化のコストが反映されている分、価格差が埋まらないのが実情です。
また、オーディブルでの単品購入は、返品や再生のしやすさという利点もありますが、そもそも「何度も聴き返したい作品かどうか」がはっきりしていない段階では、購入に慎重になる人がほとんどです。「高いのに失敗できない」という心理的ハードルが、利用者にストレスを与える要因になっています。
さらに、オーディブルにはKindle Unlimitedのような「まとめ買い割引」や「セット割引」のような制度がないため、シリーズ作品を1冊ずつ単品で購入していくと、出費がかさみやすい点にも注意が必要です。
このように、単品購入は作品を厳選して買うべきスタイルになりますが、「気軽に読書(聴書)を楽しむ」というオーディオブックの利点を活かしきれなくなる可能性もあるため、コスパ重視で使いたい方には不向きと言えるでしょう。
デメリット3「ながら聴き」が頭に入らない
オーディブルは「耳だけで読書ができる」のが大きな魅力ですが、ながら作業中に聴いても内容が頭に入らないという声は少なくありません。特に通勤中や家事中、運動中など、別の行動に意識が向いていると、気づけば話が進んでいて内容が理解できなかった…という経験をする方は多いです。
これは、聴覚情報の処理には一定の集中力が必要だからです。人は視覚からの情報には慣れていても、聴覚のみで情報を処理することにはあまり慣れていません。そのため、「聴く読書」は、特に初心者にとっては集中力が分散しやすく、記憶に残りにくく感じられるのです。
また、オーディブルの作品には図表や付属資料がある場合もありますが、これらはスマホ画面で確認する必要があるため、ながら聴き中は参照が困難です。こういった「視覚情報が補えない」という特性も、内容の理解を妨げる要因になります。
対策としては、次のような工夫が効果的です。
- 頭を使わない単純作業中に聴く(例:散歩、皿洗い、洗濯物たたみなど)
- 一度聞いて理解が浅かった部分は、意識的に巻き戻して再聴する
- ビジネス書や専門書よりも、ストーリー性のある小説やエッセイを選ぶ
特に初心者の方には、まず「内容が気になって自然と耳が傾く」ような軽めの作品から始めるのがおすすめです。また、オーディブルの再生速度を少し落とすことで、聞き取りやすさが大幅に向上する場合もあります。
「ながら聴き」がうまくいかないと感じたら、それはあなたの集中力が低いのではなく、聴き方と作品の相性が合っていないだけかもしれません。少しずつ耳を慣らしながら、自分に合った聴き方を見つけることが大切です。
デメリット4 ナレーターの声が合わないとつらい
オーディブルの魅力のひとつは、プロのナレーターが本を朗読してくれることです。しかし、裏を返せば「声の相性」が体験の満足度を大きく左右するという点が、見落とされがちなデメリットとなります。
実際に、いくら内容が魅力的な作品でも、ナレーターの声質が合わなかったり、語り口調に違和感を覚えたりすると、集中できずにストレスを感じることがあります。特に小説の場合、登場人物のセリフをすべて1人で演じるため、「このキャラにこの声は違う」と感じてしまうと、物語に没入できなくなることもあります。
たとえば、男性主人公の一人称視点なのに女性ナレーターが朗読していたり、抑揚が少なく機械的に感じる読み方だったりすると、聞いていて違和感を覚えるケースが多いです。また、逆に演技が過剰でわざとらしく聞こえる場合もあり、リスナーによって好みが大きく分かれるポイントでもあります。
このような「ナレーターとの相性問題」は、紙の本や電子書籍にはない、オーディオブックならではの難しさです。しかも、内容とは関係のない部分で聴く気が失せてしまうというのは、利用者にとっては大きなストレスになりかねません。
ただし、オーディブルは聴き放題サービスなので、合わないと感じた作品をすぐに切り替えられるのは大きな救いです。気に入らない声の作品に固執する必要はありません。むしろ、ナレーターとの相性がよかった作品を見つけたら、その人が朗読している他の作品を探すという楽しみ方もできます。
ナレーターの声に違和感を覚えたときは、「自分には合わなかっただけ」と割り切って、気持ちを切り替えるのがポイントです。声の相性は、聴く人の感性に強く依存するため、万人に合うナレーターはいないという前提で利用するのが賢い使い方です。
デメリット5:ちょっと戻る・メモが不便
オーディブルは「耳で聴く」スタイルのため、紙の本や電子書籍のように、気になった箇所へすぐに戻ったり、メモやマーカーを引いたりするのが難しいという弱点があります。特にビジネス書や学習系の作品では、「今の説明、もう一度聞きたい」「あとで見返したい」と感じる場面が多く、こうしたときに不便さを実感しやすいです。
「30秒戻る」などの巻き戻し機能はアプリに備わっていますが、スマホが手元にない状況や、家事・運転などの「ながら聴き」中は操作自体がストレスになります。また、Bluetoothイヤホンで操作できる場合もありますが、機種によって設定や動作が異なり、慣れるまでは手間取ることがあります。
さらに、読書中の気づきや大事なポイントを「記録する」という点においても制約があります。オーディブルには「クリップ機能」や「メモ機能」が存在しますが、操作が直感的ではなく、どこに何を書いたかを後から探しにくいという声もあります。視覚的に情報を整理したい方や、マーカーで要点を色分けして覚えるタイプの方には、大きなデメリットといえるでしょう。
この不便さに対して、メモアプリや紙のノートを併用する方法もありますが、再生を一時停止したり、巻き戻したりしながら書く必要があるため、手間がかかります。短時間で要点を把握し、効率よくインプットしたい人にとっては、オーディブル単体では完結しにくい場面も多いです。
特に「学び目的で聴く」ユーザーにとっては、オーディブルの情報取得スタイルが「記憶に残りにくく、整理しづらい」と感じる原因にもなり得ます。娯楽目的の聴書ならさほど気にならないかもしれませんが、実用書や専門書を扱う際には、この「戻りにくさ」「メモしにくさ」が足かせになる可能性があります。
デメリット6:退会後は聴けなくなる(例外あり)
オーディブルの大きな特徴であり、注意すべき点のひとつが「退会後は聴き放題の作品が聴けなくなる」ことです。これはAmazon Audibleがサブスクリプション型のサービスであるためで、契約期間中のみ、対象のオーディオブックが聴けるという仕組みになっています。
たとえば、月額会員として毎月1,500円を支払っている間は、20万冊以上の作品を自由に聴くことができますが、退会した瞬間からそのライブラリはすべてロックされ、アプリ上でも再生できなくなります。これは、SpotifyやNetflixなど他の定額制サービスと同様の扱いです。
しかし、すべての作品が退会後に聴けなくなるわけではありません。例外として「コインやセール、通常購入で単品購入した作品」は退会後も聴くことが可能です。購入という形で入手したタイトルは「自分の資産」としてライブラリに残るため、いつでも再生することができます。
この点を知らずに契約を終了してしまうと、「ダウンロードしてあるから聴けると思っていたのに再生できない」といったトラブルが起こることがあります。ストリーミング再生だけでなく、端末にダウンロードしていたとしても、あくまで契約状態が再生の前提となるため注意が必要です。
また、「もう一度聴きたい」と思って再入会した場合でも、以前聴いていたタイトルが聴き放題対象外に変更されていることもあるため、退会前に本当に聴き終えたい作品をチェックしておくことが重要です。
オーディブルを効率的に使いたい方は、「無料体験中にまとめて聴く」「単品で繰り返し聴きたい本は購入する」といった工夫を取り入れることで、退会後の後悔を防ぐことができます。サブスク型のメリットを活かしつつ、損をしない使い方を意識して活用することが大切です。
デメリット7 アプリの操作性にややクセがある
オーディブルのアプリは、直感的に使いやすいという声がある一方で、「慣れるまで少し戸惑う」「細かい操作がしづらい」と感じる人も少なくありません。特にITに不慣れな方にとっては、再生・停止・巻き戻しといった基本操作以外が分かりづらく、使いこなすまでに時間がかかることがあります。
たとえば、再生速度の変更はワンタップでできる範囲が限定されており、0.7倍・1.0倍・1.2倍など、あらかじめ決められた速度しか即座に変更できません。それ以外の速度に調整したい場合は、スライドバーで微調整する必要があり、思った通りの速度に合わせるのがやや面倒です。
また、アプリ内での「クリップ(しおり)機能」や「メモ機能」は存在するものの、視覚的にどこをマークしたのかが把握しづらく、一覧性が低いという欠点もあります。読み返したい箇所をすぐに探すには向いておらず、「メモしたのに後から活かしにくい」と感じる方もいるでしょう。
さらに、オフライン再生用にダウンロードした作品の管理画面が少し複雑で、「どれが聴き放題で、どれが単品購入か」がパッと見で判別しにくい仕様となっています。このため、複数の作品を同時に聴いている場合や、過去に購入した作品が多いユーザーにとっては、ライブラリの整理がしにくいという声もあります。
他社アプリと比べて、全体の設計はしっかりしているものの、「カスタマイズ性」や「操作時の軽快さ」においては、やや改善の余地があるといえるでしょう。特にスマホに不慣れなユーザーや、読みながらメモを取るような使い方をしたい人には、もう一歩の使いやすさが求められます。
このように、アプリの操作性は人によって「ストレスなく使える」と感じるか、「使いづらい」と感じるかが分かれやすいポイントです。最初は戸惑うことがあっても、再生速度やメモ機能の使い方に慣れていけば、快適に活用できるようになるケースも多いので、無料体験中にじっくり試してみるのがおすすめです。
それでもオーディブルを使う理由とは?
オーディブルには「聴き放題の対象が限られている」「ナレーターとの相性」「メモ機能の使いにくさ」など、いくつかのデメリットがあります。しかし、それらを踏まえた上でも、なお多くのユーザーがオーディブルを使い続けているのには、明確な理由があります。ここではその代表的な理由を解説します。
耳さえ空いていれば読書ができるという圧倒的な利便性
最大の魅力は「目と手がふさがっていても、耳で本が読める」点です。通勤・通学中、料理や洗濯などの家事中、あるいはジムでのトレーニング中でも、音声で本を楽しめるのは他の読書スタイルにはないメリットです。普段は読書時間を確保できないという人でも、日常のスキマ時間を「知識のインプット時間」に変えることができます。
読書量が自然に増える
オーディブルを利用すると、1日1〜2時間は読書にあてられるようになるという声も珍しくありません。紙や電子の読書とは違い、物理的な「読書のための場所」や「集中できる時間」を用意する必要がないため、結果的に読書量が増えるのです。特に普段から「本を読みたいのに時間がない」と感じている方にとっては、大きな味方となります。
感情のこもった朗読で「活字よりも印象に残る」ことがある
プロのナレーターによる朗読は、ただの音声再生とは違います。物語の世界観や登場人物の感情がリアルに伝わり、印象が強く残ることがあります。特に文学作品やエッセイなどでは、紙の本よりも深く物語に入り込めるという人もいます。文章を「読まされている」のではなく、「語りかけられている」感覚が、読書体験をより豊かにしてくれます。
無料体験で合うかどうかを気軽に試せる
オーディブルは30日間の無料体験を提供しており、聴き放題対象の作品であれば何冊でも試すことができます。もし「やっぱり合わない」と感じたら、無料期間内に解約すれば料金は一切発生しません。この「リスクゼロ」で試せる点は、ITサービスに不慣れな方でも安心して利用を始められる大きなポイントです。
ピンポイント利用でも十分に元が取れる
「毎月1,500円はちょっと高い」と感じる方もいるかもしれませんが、例えば話題のビジネス書や小説を1冊でも聴けば、それだけで元が取れるケースも少なくありません。たとえば通勤中に1冊聴き終えることができれば、それは「本1冊をまるまる無料で楽しめた」のと同じ。特に無料体験中に気になる作品をまとめて聴くスタイルであれば、コスパはさらに高まります。

オーディブルは、確かに万人にとって最適なサービスではありません。しかし、「耳を使ってインプットする」というスタイルが自分の生活にマッチするのであれば、これほど効率的かつ自由度の高い読書手段は他にありません。デメリットを理解したうえで、自分に合う作品・使い方を見つけられれば、オーディブルは日々の生活に新しい価値をもたらしてくれるサービスとなるでしょう。
【30日間の無料体験はこちら】
audible(オーディブル)公式サイトはこちら
向いている人・向いていない人の特徴
オーディブルは便利な一方で、すべての人に合うサービスではありません。ここでは、利用者のタイプ別に「向いている人」と「向いていない人」の特徴を整理し、自分にとって適しているかどうかを判断しやすくします。
オーディブルが向いている人
- スキマ時間を有効活用したい人
通勤・家事・運動中など、耳だけが空いている時間を有効に使いたい方にはオーディブルがぴったりです。時間に追われがちな方でも、読書を日常に取り入れやすくなります。 - 文字を読むのが苦手、もしくは目が疲れやすい人
目が疲れやすい方や活字離れしてしまった方でも、音声であれば無理なく本の内容を吸収できます。老眼や視覚障害を持つ方にも支持されています。 - ストーリー性のある本が好きな人
小説やエッセイ、朗読に適したジャンルの本を楽しみたい方には、ナレーターの表現力も加わり、没入感ある読書体験が得られます。 - 一冊をじっくり繰り返し聴きたい人
お気に入りの本を何度も聴いて理解を深めたい人には、オーディブルの再生・巻き戻し機能が役立ちます。リスニング学習にも向いています。 - 耳からの情報処理が得意な人
音声でのインプットが得意なタイプの方は、オーディブルをストレスなく使いこなせる傾向があります。ポッドキャストやラジオを好む人も該当します。
オーディブルが向いていない人
- 図解や表を見ながら理解したい人
ビジネス書や学術書のように、図表を見ながら読み進めたい人には不向きです。視覚情報が必要な内容は紙の本や電子書籍のほうが適しています。 - 読んだ部分にマーカーを引いて整理したい人
オーディブルでは、簡単に線を引いたりページをめくったりすることができません。メモや要点の整理を重視する人にとっては不便に感じるでしょう。 - 再生速度や音声の調整に手間を感じる人
アプリ操作に慣れていない人や、自分好みにカスタマイズするのが苦手な人には、アプリの機能や設定がやや煩雑に感じられるかもしれません。 - 聴覚より視覚で記憶するタイプの人
耳からの情報が入りづらく、読んで覚える方が得意な人には、オーディブルの学習効果が感じにくい可能性があります。 - 聴く環境を確保しづらい人
家族と同居していたり、静かな環境が確保しにくい生活スタイルだと、オーディブルの音声再生に集中しづらい場面が出てきます。

オーディブルの活用には「自分の情報処理スタイルや生活リズム」との相性が非常に重要です。上記のポイントを参考に、自分がどちらのタイプに近いかを確認してから、無料体験でお試しするのが最もリスクのない方法です。
【30日間の無料体験はこちら】
audible(オーディブル)公式サイトはこちら
無料体験で自分に合うか確かめるのが最適解
オーディブルは「耳で聴く読書」という独自のスタイルのため、人によって合う・合わないが大きく分かれます。これまで紙の本や電子書籍でしか読書してこなかった方にとって、最初は違和感を覚えることも少なくありません。「本当に自分に向いているのか?」と不安を感じたら、無料体験で実際に使ってみるのが最も確実な方法です。
オーディブルはAmazon公式で30日間の無料体験を常時実施しており、その間は20万冊以上の聴き放題コンテンツを自由に試すことができます。登録時に支払い情報の入力は必要ですが、無料期間中に解約すれば料金は一切かかりません。解約もアカウント設定画面から数クリックで完了し、違約金などもありません。
たとえば「通勤中に聴いてみたい」「家事をしながら試したい」といった日常の中で自分のライフスタイルと相性が良いかどうかを確かめられます。聴くスピードやナレーターとの相性、アプリの操作感も含めて、30日間でじっくり確認できるのは大きなメリットです。
また、もし合わないと感じたとしても、1冊だけでも聞いて「この作品だけはよかった」と思えるものに出会えれば、それだけでも無料体験の価値はあります。逆に「何を聴いても頭に入らない」「ナレーターの声がどうしても合わない」と感じる場合は、素直に見送る判断もできます。

オーディブルに興味はあるけれど、デメリットが気になるという方こそ、まずはこの無料体験を活用して「自分にとって価値のあるサービスかどうか」を見極めるのが、失敗しない賢い選択です。迷う時間があるなら、1冊でも実際に聴いてみることで、判断材料が一気にクリアになります。
【30日間の無料体験はこちら】
audible(オーディブル)公式サイトはこちら